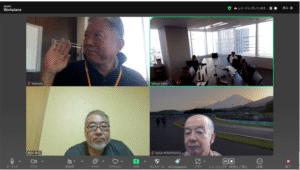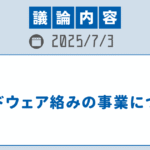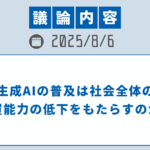【活動報告記事】2025年7月26日
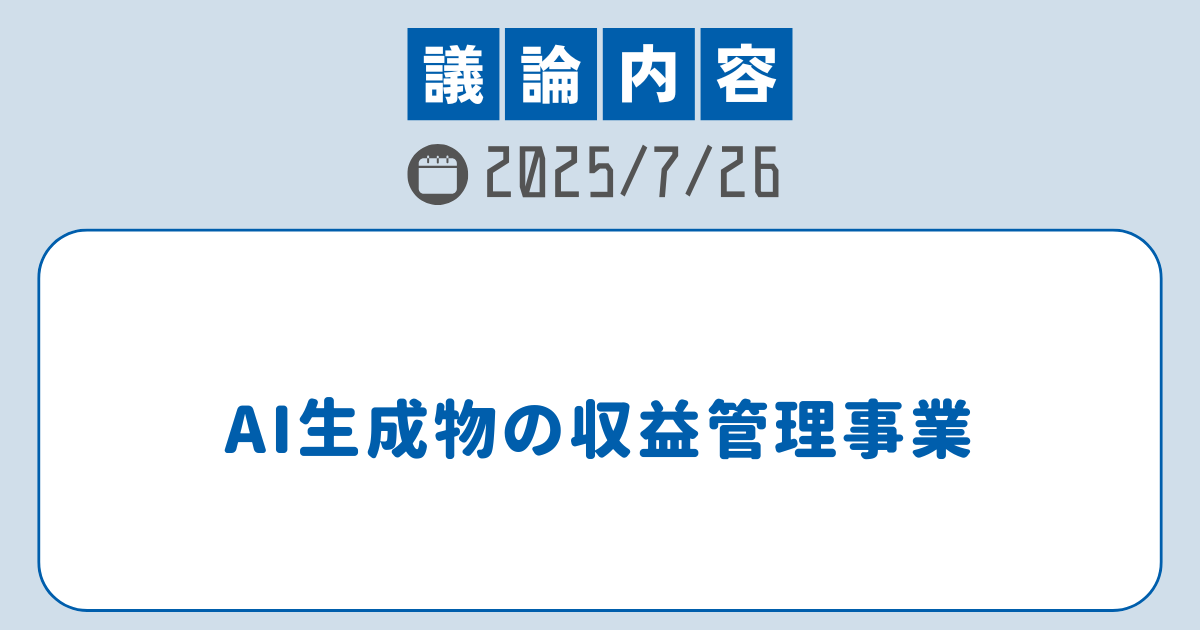
その前に「生成AIゼミ」も行い、本日は「AIが獲得した知識はどこに行くのか?」について議論しました。プロンプトはオプトアウトしたり、有償版を使用することにより「学習しない」条件で使用できるものが増えていますが、実体験として多くのユーザが打ち込んだ内容はそのうちエージェントの回答に反映されていると感じることがあります。
果たしてこの現象はどのような機序で起きているのかについて多少の推測も含めて議論が盛り上がりました。プロンプトそれ自体は学習の対象とならないとしても、多くのユーザが同様の内容を打ち込むとそれがそのうちエージェントの回答に反映されているという体験を複数のユーザがしていることから、「集合知」としてその内容がエージェントの知識として“染み出している”のではないか、という意見が出ました。
本当のところがどうなっているのかは確認の仕様がありませんが、「発明の新規性」の有無を扱う知財専門家としては大変興味深い議論の切り口が発見されたようです。
本論では、以前から議論してきた「出願人」が誰になるのかについて一定の結論に達した重要な機会となりました。新規事業は計画通りにいかないことも多くあり、本件でも様々な内部環境、外部環境の変化が起こりましたが、この時点で一旦誰が権利を持つべきか、という議論に終止符が打たれたことは大きな意味があります。
幸いにして、議論に参加した各メンバーがそれぞれの視点・経験に基づいてベストと思われる結論となりましたので、事業オーナー自身もすっきりして次の行動の検討を始めることができるようになりました。
知財アナリストとしては、顧客に対してこのような「権利のオーナーシップ」のアドバイスを行う機会は多くあるのですが、改めて「自分事」としてこの問題について正面から向き合うことで、体感としてその問題の大きさと正しい判断をする効果の双方を経験できたことは、それぞれの業務スキルに大きな向上をもたらしたことは間違いないようです。
当会は単なる権利化の観点ではなく、本件のように事業計画との関係で本質的な議論もできる専門家コミュニティとして新たなご相談をお待ちしております。