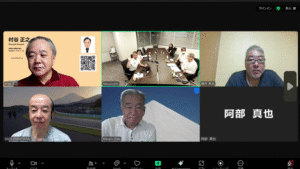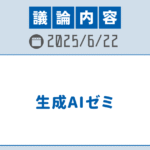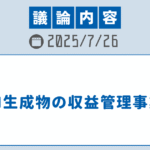【活動報告記事】2025年7月3日
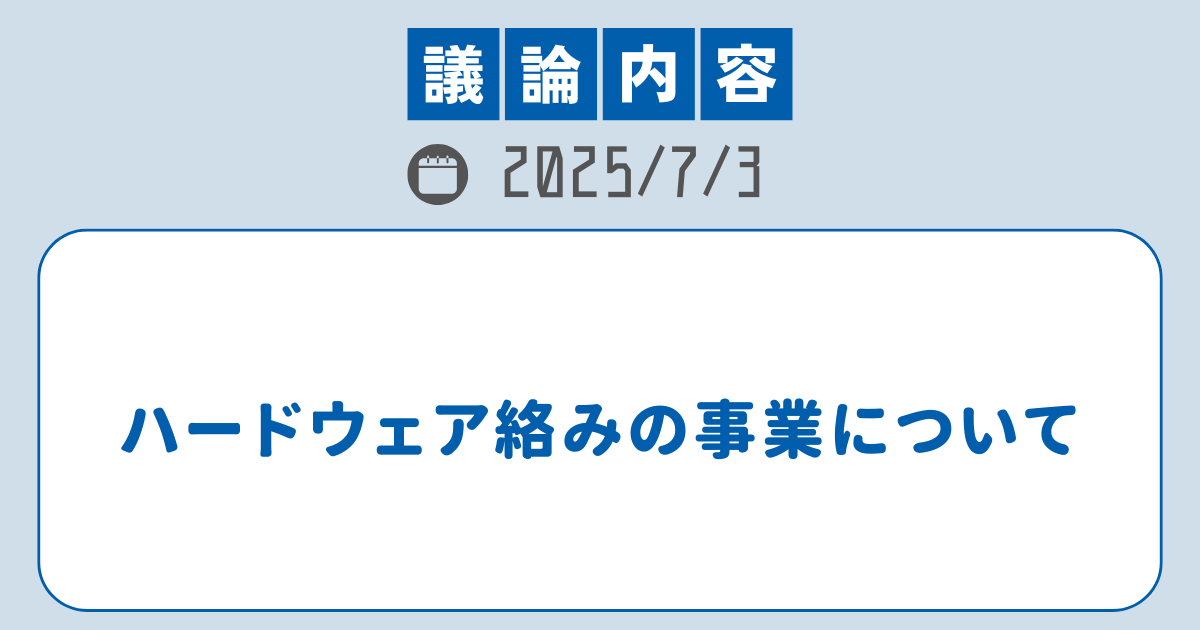
以前から何度か議論しているテーマですが、今や貴重な存在となっている電子基板から設計できるメーカーの方の新規事業で気候変動対策に関するソリューションを提供するものです。
今回はプロトタイプデバイスが完成したとのことで現物を見ながらいかに販路を拡大していくかについていつものように多方面からの質問やコメントが飛び交いました。
事業オーナーの方のご希望もあり、デバイスそのものの特許ではなく、これを活用したアプリケーション寄りの発明に着目してビジネスモデル特許を特定することに議論の主眼を置きました。
複数の会員から新規事業ではコア技術よりもむしろ周辺技術が重要になることがあること、そのあたりの工夫はラボでは情報が少なく現場で使ってもらうことで初めて気付きに繋がることが経験談として語られました。
そして、最終的に辿り着いた知見は、キーデバイスの供給元の大学との共同出願の是非に関するものでした。事業オーナーとしては、キーデバイスの制作費用と引き換えに発明の持ち分を譲渡する構想で臨まれていましたが、共同出願・共同特許の使い勝手、ライセンス等将来の成長戦略への影響等を多面的に考慮すると、コンセプト特許であっても単独出願することの重要性について時間をかけて議論したおかげで事業オーナーとしても知財の活用イメージについて新たな知見が得られたようでした。
特にスタートアップや中小企業にとって知財のコストは安いものではなく、開発投資と同様にキャッシュ負担が重いのが通常ですが、どこにどれだけキャッシュを投資するのかの検討と並行して、その投資をした知財をどのように活用できるののかについて前もって検討を加えていくことで「事業計画」のブラッシュアップに繋げることができる、という「一石二鳥」の「発明ブレストの効果」を改めて感じ取ることができたセッションでした。